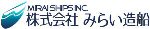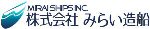
。。。 Hokkaido Branch Factory
造船気質ーアルミ小型漁船の建造工程
初級・一般向け
建造工程フロント -初期から引渡しまでの流れ
1)初期段階
1.船主打合せ 船主建造依頼・出向き営業→打合せ→基本設計→見積
2.契約前 船主見積調整→関連業者仕様・見積の確認→納期取決めて契約
3.契約後 建造申請→主材・主機関注文→船主に工程・仕様の再提出
2)船殻初期工程 (起工式は この工程に行われます)
4.設計・現図 基本設計→詳細設計(現図)→部材型出力及びマーキング
5.現場地上小組 部材切断→部材に骨材付け→小組立→外板曲げ
3)船殻大組工程
6.ブロック組立・溶接 アッパーデッキから甲板下ブロックを倒立状態で組立
7.甲板下ブロック治具搭載 甲板下ブロック骨組組立後治具搭載→ブルワーク取付
8.倒立ブロック完成 全体の骨組完成後→下向溶接→外板貼付→外板溶接
9.ブロックを正立に反転 反転→下向溶接→歪取り→外板サンダー仕上げ
4)並行する上部構造物及び各種艤装工事
10.上部構造物組立 上部構造・艤装設計→ケーシング組立→マスト類組立
11.各種地上艤装工事 甲板・機関室の機器類の架台製作→先行配管・配線
5)搭載・艤装工事
12.主機関及び機器類搭載 各部歪取り後→シャフト系芯出し→主機関搭載
13.上部構造搭載 機関据付後ケーシング搭載→艤装構造物搭載
6)進水
14.塗装工事・進水前点検 舵取付→塗装→外舷・貫通周りチェック
15.進水 進水式→艤装岸壁にて主機始動・残艤装工事
7)海上試運転
16.試運転・データー取り 船主立会い試運転→公試運転
17.効力試験 各機器類及び航海・漁労機械の試運転調整→仕上艤装工事
8)引渡し・回航
18.回航準備 最終総合機能チェック→回航準備→回航
19.引渡し 漁具搭載→初回操業確認後→引渡し完了
9)アフターサービス
20.アフター契約 1年補償期間後はアフター契約
建造工程フロントに戻る
1)初期段階
1.打合せ段階 <船主建造依頼→打合せ→基本設計→見積>
船主直接か動向があって タイプシップを調査し打合用図面を持って伺います
船の用途・性能・大きさ及び機器の選択、 そして納期関係を詰めて協議し、
まずは 見積できる概略基本設計し一般配置図を完成させます、 この時点で
意思のある図書と自信をアピールできたなら、 ライバル造船所競争におい
ては優位に進めることが出来ますが・・、 まだ予断のならぬ段階ではある。
2.契約前の段階 <船主見積調整→関連業者仕様・見積の確認→納期取決めて契約>
船主の予算・希望に合わせて見積金額・仕様の話合いに入ります、 ここでは造船所
が船を合理・機能的にシステム(船)全体を思考し船主に適正金額を示す能力が鍵。
造船所が不甲斐無いゆえ 船主が直接主機メーカー・商社に見積依頼し見込予算からの
お釣りが造船所所掌でそれから造船所数件に見積らせるなんての構図は過去だけの
ことにしてもらいたい。 こういう構図はありえない、 しっかりせい造船所。
3.契約後の段階 < 建造申請→主材・主機関注文→船主に工程・仕様の再提出>
漁船の場合、 建造前に関係各省に建造許可申請をします。 許可後から建造工程に入り
納期のかかる船体主材(アルミ材)、 主機関、 漁労機械などは直ちに注文します。
工程表、 機器納入表を練って 確実に納期が決まれば、 船主及び関連機関(漁組 等)に
仕様書・工程(出来高)表を提出し、 お互いの信用確認のうえ 全力を誓います。
建造工程フロントに戻る
2)船殻初期工程
4.設計 <基本・構造設計→現図→部材型出力及びマーキング>
基本設計(アレンジ、 ライン、 コンプロ)の時間のかけ方・醸し方いかん
によって 船の性能のレベルが高まります。 膨大な数の構造部材をCADで
書いてプロッター出力しフィルム型と定規をマーキング班に渡せばもう
後には戻れません。 設計者の不安? を無視して現場工程はシステムに
従い、 各エキスパートに渡りどんどん進みます。
| 基本設計→ | 詳細設計で現図)→ | パーツ ネスティング→ | ケガキ作業 |
 |
 |
 |
 |
5.現場地上小組 <ノコ切断→部材に骨材付け→小組立→外板曲げ>
アルミ板に書かれたマーキング通りに丸ノコ(100Φ・160Φ)で
切断します 動力は電気・エアーです。 切断された部材に骨付けをして
小組段階にかかります、 切断された曲げのある外板は 曲げ加工にまわします
バーナーであぶり水をかけながら 縮む力で職人技を持って曲げられます。
建造工程フロントに戻る
3)船殻大組工程
6.ブロック組立・溶接<アッパーデッキから甲板下ブロックを倒立状態で組立>
地上にて アッパーデッキの cutting・板接ぎをして
マーキング→切断の後 いよいよ前加工した 部材を倒立状態
にて組上げていきます、 あらためて 部材の多さには 閉口する
船尾甲板下ブロック・船首甲板下ブロックに分け この段階
は進みます ねじれ・ゆがみの無い様に工作精度に神経集中。
| U.DECKマーキン→ | U.DK組立→ | 骨材組上げ→ | 甲板下ブロックジグ搭載前→ |
 |
 |
 |
 |
7.甲板下ブロック治具搭載<ブロック骨組組立後治具搭載→ブルワーク取付>
甲板下骨組みブロックを地上で簡易治具にて組上げた後
船尾甲板下骨組みブロックから、 ブルワーク分 高さを考慮した
鋼製治具を立て 搭載します、 その時の注意は 水平と基準線 が
ポイントとなります。 船尾からの基準が決まれば 船首甲板下
骨組みブロック→船首楼ブロック→ブルワークの順に搭載します。
| 船尾ブロック先搭載→ | 船首ブロック搭載→ | 船首楼組上げ→ | ブルワーク搭載→ |
 |
 |
 |
 |
8.倒立ブロック完成<全体の骨組完成後→下向溶接→外板貼付→外板溶接>
全体骨組みブロックが完成したら 骨組みの溶接です
ミグ溶接機という 半自動溶接機で この状態で 下向き溶接と
できる限りの 垂直上り溶接をやります その後 船首楼外板→
ブルワーク外板→ボットム外板と精度良く曲げた外板を貼り付
けます 外板の溶接まで終えたら 第1回目の反転の準備となります。
| 骨組の溶接→ | 船首外板貼付→ | スタンフレーム搭載→ | 外板溶接完了→反転 |
 |
 |
 |
 |
9.ブロックを正立に反転<反転→下向溶接→歪取り→外板サンダー仕上げ>
クレーン(25t)2台での反転作業(造船屋はトンボと言います)
反転後は下向溶接の山です 溶接終了後→外から射水テスト→
タンクエアー圧力テスト 等 社内及びJCIの諸検査を行います。
艤装工事と平行し 外板の歪を取り 溶接の応力を抜き引き締めます
歪の無い面が整えば ディスクサンダーで丁寧に仕上げていきます。
| 大量の下向き溶接→ | 最終3回目反転→ | 外板歪取り→ | サンダー仕上げ→ |
 |
 |
 |
 |
建造工程フロントに戻る
4)並行する上部構造物及び各種艤装工事
10.上部構造物組立<上部構造・艤装設計→ケーシング組立→マスト類組立>
艤装工事も船殻工事と並行しておこなわれ 搭載機器による
各船の違いもあり 設計者はこの時点から 戻り工事の無いように
納入業者・船主殿と図面、 図書を基に綿密に打合をし進行します
上部構造物は 主機関搭載に合わして すぐ搭載できる様に
基本工程が組まれます どれひとつ遅れても システムに影響します。
| 操舵室正面→ | 甲板室 船尾より→ | レーダーマスト組立→ | 船首マスト組立→ |
|  |
 |
 |
 |
11.各種地上艤装工事<甲板・機関室の機器類の架台製作→先行配管・配線>
航海・漁労・機関・甲板機器類の架台及び製作物(すごい数です)、
作業効率を考え 外板張る前とか 倒立ブロック状態でも
出来る作業は行います (これを 先行艤装という)
配管等のフランジ・貫通金具・配管・架台類の取付 等がある
工程を考えた場合 やるとやらないでは とんでもない差が。
建造工程フロントに戻る
5)搭載・艤装工事
12.主機関及び機器類搭載<各部歪取り後→シャフト系芯出し→主機関搭載>
外板・バルクヘッド・アッパーデッキの歪取りを完工してから
機関台より軸心サイトし スタンチューブを取り付けます
プロペラシャフトを通してしまえば 主機関の搭載です
主機関据付→主機前カウンター据付→発電機据付と機関室
内部に大物を先から納め 上部構造を搭載する段取りをします。
| スタンチューブ取付→ | 舵、 ペラと取付→ | 機関搭載前→ | 機関芯出し取付→ |
|  |
 |
 |
 |
13.上部構造搭載<機関据付後ケーシング搭載→艤装構造物搭載>
上部構造搭載後に 測度 という船の大きさの指標を
測る検査があります どこの造船所もあまり好きでは・・・・
この時点の工事状況は 怪我や災害の多いタイミングで
電線・ガスホース関係が込み合い 機関室内、 甲板に
人が集中するので。 社内安全システムの徹底を誓います。
| 上部搭載前→ | 上部構造搭載→ | 油圧漁労機械→ | 漁労機械搭載位置出し→ |
|  |
 |
 |
 |
建造工程フロントに戻る
6)進水
14.塗装工事・進水前検査<舵取付→塗装→外舷・貫通周りチェック>
舵・プロペラを取り付け→シーチェスト及び貫通関係、
外舷まわりの工事が完了して 塗装工事にかかり 船名を
書けば JCI進水前検査、 水産庁認定検査、 等 で進水前の
工事が完了します。 進水後すぐ主機関を始動できる工程も
あれば、 進水後艤装岸壁でしばし の工程の場合もある。
15.進水<進水式→進水→艤装岸壁にて主機始動・残艤装工事>
進水式後は船舶設計者は ほとんど普通の状態ではありえない。
現状態での計画喫水通り浮くだろうか? とか 浮き姿はどうだ
計画通りの性能が出るだろか、 スピードギャランティーなど
あれば 前の日から ほったらかして 何処かに行きたい衝動に・・・・
ま、 まな板の鯉状態ですから・・ 一様、 平気な顔してますが・・・。
| 進水式前(さんま) | 進水式前(ホタテ) | 進水式典 | 餅撒き |
 |
 |
 |
 |
建造工程フロントに戻る
7)海上試運転
16.試運転・データー取り<船主立会い試運転→公試運転>
エンジン始動したら、 法定検査の臨時航行検査を受験し、いよいよ
社内試運転です 検査的と社内独自の試運転メニューに従い進みます。
性能がそこそこ以上だと、 本当に ホッ〜 とし 心地よい睡魔が・・・
船主さん引き取ってくれますか?・・・・ 「マア〜いいんじゃない。」
くらい言わせたら 嬉し疲れで もう酒飲んで寝たい気分になる。
駄目なら 目をギンギラにして 必死で対策を探り言い訳して絶対に
何とかする。 試運転データー確認後は法定検査の公試運転と言う
法定の最終検査を終え、 JG・JCIから検査証書をいただきます。
| 19GTサンマ | 14GTホタテ船 | 29GT-JG公試 | 19GT-JCI公試 |
 |
 |
 |
 |
17.効力試験<各機器類及び航海・漁労機械の試運転調整→仕上艤装工事>
各機器の効力テスト いわば 性能通り動くかどうか テストします
船の試運転航行に比べれば 所詮出来物の試運転 動いて当り前
これからの 仕上げ艤装が総てです これに手を抜くと 良い物使って
金かけて、 頭絞った甲斐も無くなります だから気は抜かない!
後工事の無い様に 経営者・設計者は 船主べったりで確認します。
| サンマLED集魚灯 | 内部電機・航海計器 | 油圧圧力 | 外部電機・航海計器 |
 |
 |
 |
 |
建造工程フロントに戻る
8)引渡し・回航
18.回航準備<最終総合機能チェック→回航準備→回航>
最終総合機能チェックにたっぷり2時間以上の時間をかけて
回航スピードより高め(ほぼ全速)の続航テストで回航の自信を
付けます、 2人の回航屋が2月の真冬海を回航することもあり
絶対に事故のないように回航出航と同時に造船所も車で陸か
ら船を横に見ながら並走します。 何事も慎重過ぎるほどに。
19.引渡し<漁具搭載→初回操業確認後→引渡し完了>
現地で造船所も 愛娘(船)を迎えます、 漁具を積み込み、 最終調整艤装し
初出漁後の点検をして、 娘をさらった おっさんに 有難うございました
娘をよろしくお願い致します語って、具合が悪ければすぐ診にきますとか
言って寂しい気持ちでいっぱい。 社員全員が船に情が入っちゃって大変
なんだけど、祝引渡しです。 船主はいろんな緊張でいっぱいだしね。
| 嫁ぎ先に入港→ | 初操業立会い→ | 満載ですお疲れ!→ | 20トン帰港状態→ |
 |
 |
 |
 |
建造工程フロントに戻る
9)アフターサービス
20.アフター契約<1年補償期間後はアフター契約>
1年とか、 その後とか 寂しい話だよね ずっと親戚付き合い
みてえ〜な もんでしょ 縁があって 建造させて頂いたんだもの
後々も船主様に得して頂きます、 オーダー工事発注も承ります。
1年後のアフターサービスのシステムを定めて伺っています。
これからは物持ちの時代、 末永く使いましょう 道具です
アルミ船は使うほど メインテナンスするほど 一生ものです。
| アフター工事は真冬 | さ・・寒い | 漁保修理 | ダブリング修理 |
 |
 |
 |
 |
建造工程フロントに戻る
┃ホーム┃
|